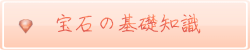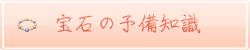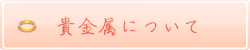アクアマリンの組成

- 分類:ケイ酸塩鉱物
- 組成:Be3Al2Si6O18
- 結晶系:六方晶系
- 色:アクアマリン
- モース硬度:7.5
アクアマリンの特徴
以下では、アクアマリンの特性、産地、色に関して解説します。
アクアマリンの特性
アクアマリン(和名は藍玉-あいぎょく)とは、ベリル(緑柱石/Beryl)のうち透明でスカイブルーの色調のものを指します。海に投げ入れると即座に見失ってしまうほど海の色に溶け込みやすく、古いヨーロッパの船乗り達は、この石を海の力の宿ったお守りとして大切に持っていたと言います。名前はラテン語で「海の水」を意味する「aqua marina」に由来しています。
アクアマリンの産地はブラジルが有名ですが、それ以外ではスリランカ、マダガスカル、ロシア、パキスタン、アフガニスタン、インドなどが産地として挙げられます。アクアマリンの特殊効果としてはキャッツアイがありますが、非常に稀少で市場ではあまり見られません。石言葉は「勇敢」で、ブラッドストーンと共に3月の誕生石とされています。
アクアマリンの産地はブラジルが有名ですが、それ以外ではスリランカ、マダガスカル、ロシア、パキスタン、アフガニスタン、インドなどが産地として挙げられます。アクアマリンの特殊効果としてはキャッツアイがありますが、非常に稀少で市場ではあまり見られません。石言葉は「勇敢」で、ブラッドストーンと共に3月の誕生石とされています。
ブラジルとアクアマリンの関係
ブラジルとアクアマリンとは切っても切れない関係にあります。
産出量は枯渇しつつあるものの、ブラジルのサンタマリア鉱山で採掘される、深いマリンブルーの石が最高品質とされており、特に「サンタマリア」(Santa Maria)と呼ばれ、また、同じくブラジルで採れる鮮やかな黄色のものは「アクアマリン・クリソライト」(Aquamarine Chrysolite)と呼ばれます。
アフリカのモザンビークで採掘されるものは色合い、品質共にブラジルの「サンタマリア」に似ていますが、前者と区別するため特に「サンタマリア・アフリカーナ」(Santa Maria Africana)と呼称されることがあります。
 またブラジルのエスピリトサント州に産するアクアマリンは、産地の名をとって「エスピリトサント」(Espirito Santo)と呼ばれ、淡いブルーが特徴です。なお1954年のブラジル・ビューティークィーンであるマーサ・ロカ(Martha Rocha)の名がついたアクアマリンもあります。
またブラジルのエスピリトサント州に産するアクアマリンは、産地の名をとって「エスピリトサント」(Espirito Santo)と呼ばれ、淡いブルーが特徴です。なお1954年のブラジル・ビューティークィーンであるマーサ・ロカ(Martha Rocha)の名がついたアクアマリンもあります。
ブラジルは時に、信じられないほど巨大なアクアマリンの結晶を産しますが、1910年、ミナスジェライス州のマランバイアで発見された110.5kg(高さ48.5cm/直径42cm)にも達するものは群を抜いています。またドイツの芸術家ベルント・ムンシュタイナーによってデザインされ、イーダーオーベルシュタインにて1992年にカットされた「Dom Pedro」と呼ばれる26kgの結晶は、カットを施されたものの中では世界最大のアクアマリンとして有名です。
産出量は枯渇しつつあるものの、ブラジルのサンタマリア鉱山で採掘される、深いマリンブルーの石が最高品質とされており、特に「サンタマリア」(Santa Maria)と呼ばれ、また、同じくブラジルで採れる鮮やかな黄色のものは「アクアマリン・クリソライト」(Aquamarine Chrysolite)と呼ばれます。
アフリカのモザンビークで採掘されるものは色合い、品質共にブラジルの「サンタマリア」に似ていますが、前者と区別するため特に「サンタマリア・アフリカーナ」(Santa Maria Africana)と呼称されることがあります。
 またブラジルのエスピリトサント州に産するアクアマリンは、産地の名をとって「エスピリトサント」(Espirito Santo)と呼ばれ、淡いブルーが特徴です。なお1954年のブラジル・ビューティークィーンであるマーサ・ロカ(Martha Rocha)の名がついたアクアマリンもあります。
またブラジルのエスピリトサント州に産するアクアマリンは、産地の名をとって「エスピリトサント」(Espirito Santo)と呼ばれ、淡いブルーが特徴です。なお1954年のブラジル・ビューティークィーンであるマーサ・ロカ(Martha Rocha)の名がついたアクアマリンもあります。ブラジルは時に、信じられないほど巨大なアクアマリンの結晶を産しますが、1910年、ミナスジェライス州のマランバイアで発見された110.5kg(高さ48.5cm/直径42cm)にも達するものは群を抜いています。またドイツの芸術家ベルント・ムンシュタイナーによってデザインされ、イーダーオーベルシュタインにて1992年にカットされた「Dom Pedro」と呼ばれる26kgの結晶は、カットを施されたものの中では世界最大のアクアマリンとして有名です。
アクアマリンの色
アクアマリンはその名が示すとおり、海を彷彿(ほうふつ)とさせる鮮やかなブルーが特徴で、濃い青色のものはマシーシェ(maxixe)などとも呼ばれます。
アクアマリンの色は日光への暴露(ばくろ)や加熱処理で白っぽく変化しますが、放射線照射で元に戻ります。アクアマリンの淡い青色は、内部に含まれる二価の鉄イオン(Fe2+)だと考えられており、一方黄色味がかったものは三価の鉄イオン(Fe3+)だとされています。なお、二価と三価の鉄イオン並存すると、マシーシェに代表される濃い青色が生まれるようです。
緑、ピンク、黄色のベリルに放射線を人工的に照射することにより、マシーシェに見られるような濃い青色を人工的に作り出すことも出来ます。
アクアマリンの色は日光への暴露(ばくろ)や加熱処理で白っぽく変化しますが、放射線照射で元に戻ります。アクアマリンの淡い青色は、内部に含まれる二価の鉄イオン(Fe2+)だと考えられており、一方黄色味がかったものは三価の鉄イオン(Fe3+)だとされています。なお、二価と三価の鉄イオン並存すると、マシーシェに代表される濃い青色が生まれるようです。
緑、ピンク、黄色のベリルに放射線を人工的に照射することにより、マシーシェに見られるような濃い青色を人工的に作り出すことも出来ます。
アクアマリンの動画
以下でご紹介するのは、パキスタン・バルティスタン州のギルギット鉱山にて採掘された天然アクアマリンの動画です。