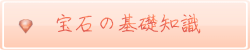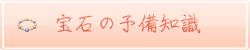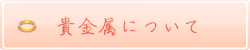ベリルの組成

- 分類:ケイ酸塩鉱物
- 組成:Be3Al2Si6O18
- 結晶系:六方晶系
- 色:薄緑、青、鮮緑、黄など
- 光沢:ガラス光沢
- モース硬度:7.5
- 比重:2.7
ベリルの特徴
ベリル(和名は緑柱石-りょくちゅうせき)は、ベリリウムを含む六角柱状の鉱物です。
小さなものから大きなものまでありますが、アメリカのメーン州では、5.5m×1.2mにも及ぶ巨大結晶が産出しており、またあらゆる鉱物の中で最も大きな単一鉱物の結晶は、マダガスカルで発見された18m×3.5mのベリルです。
小さなものから大きなものまでありますが、アメリカのメーン州では、5.5m×1.2mにも及ぶ巨大結晶が産出しており、またあらゆる鉱物の中で最も大きな単一鉱物の結晶は、マダガスカルで発見された18m×3.5mのベリルです。
ベリルの色
ベリルの中で透明で美しいものはカットされて宝石になり、色合いによって以下のような種類に分類されます。
色によるベリルの分類
- アクアマリン(ブルーベリル)鉄により淡い青色を呈するベリル。
- エメラルド(グリーンベリル) クロムやバナジウムにより、淡緑~緑色を呈するベリル。
- モルガナイト(ピンクベリル) マンガンにより淡い赤色を呈するベリル。
- ヘリオドール(ゴールデンベリル)
鉄により黄色~金色を呈するベリル。
ヘリオドールが緑がかった黄色を指すのに対し、ゴールデンベリル(golden beryl)は黄色から金色を指すという微妙な違いがあります。ゴールデンベリルの中で最大のものは2,054カラット(410g)のもので、アメリカ・ワシントンD.C.「Hall of Gems」に展示されています。 - レッドベリル
マンガンにより濃い赤色を呈するベリル。
かつては「ビックスバイト」(bixbite)という名でも呼ばれていましたが、全く同音の「bixbyite」という鉱物が存在することから、混乱を避けるために使用が廃止されました。また、。ペツォッタイトと間違われることがよくありますが、構成成分や反射率の違いから区別されます。
非常に希少な鉱物で、アメリカ・ユタ州のビーバー郡、ニューメキシコ州のシエラ郡など、世界中でも数えるほどしか産地がありません。中でもビーバー郡のワーワー山脈では、ウランを目的に調査していたラーマー・ホッジスという人物により、1958年、偶然レッドベリルの巨大鉱脈が発見されています。
上質なレッドベリルは、カラット当たりの値段がダイヤモンドのそれをしのぐことも珍しくありません - ゴシェナイト(カラーレスベリル)
アルミニウムにより色を持たないベリル。
名前は、この鉱物が最初に発見されたマサチューセッツの「Goshen」という地名に由来しています。かつてはその透明性を利用して片眼鏡やレンズなどに加工されていましたが、最近では宝飾品としての利用の方が多いようです。
ベリルの語源
ベリルの名は、ギリシア語で「青緑色の海水のような貴重な石」を意味する「beryllos」がラテン語(beryllus)、古フランス語(beryl)、中世英語(beril)などを経由し、最終的に「beryl」となったようです。
ちなみにラテン語の「beryllus」は、いつしか「brill」と省略されるようになり、現代のイタリア語「brillare」、フランス語「brille」、そして英語「brilliance」の語源となっています。意味は全て「輝く・輝き」です。
また、金属元素のベリリウム(beryllium)の名前は、この鉱物の中から発見されたことに由来しています
ちなみにラテン語の「beryllus」は、いつしか「brill」と省略されるようになり、現代のイタリア語「brillare」、フランス語「brille」、そして英語「brilliance」の語源となっています。意味は全て「輝く・輝き」です。
また、金属元素のベリリウム(beryllium)の名前は、この鉱物の中から発見されたことに由来しています
ベリルの産地
ベリルの主な産地はロシア・ウラル山脈、コロンビアの石灰岩、ノルウェー、オーストリア、ドイツ、スウェーデン、アイルランド、ブラジル、マダガスカル、モザンビーク、南アフリカ、ザンビア、アメリカなどです。ニューハンプシャー州はベリルを州石に指定しています。
ベリルの動画
以下でご紹介するのは様々なベリル亜種の動画です。
上からヘリオドール(黄/15.5 x 8.5mm/7.37カラット/タジキスタン産)、レッドベリル(赤/1.1カラット)、ゴシェナイト(無色/342カラット/ブラジル産)となっています。
上からヘリオドール(黄/15.5 x 8.5mm/7.37カラット/タジキスタン産)、レッドベリル(赤/1.1カラット)、ゴシェナイト(無色/342カラット/ブラジル産)となっています。